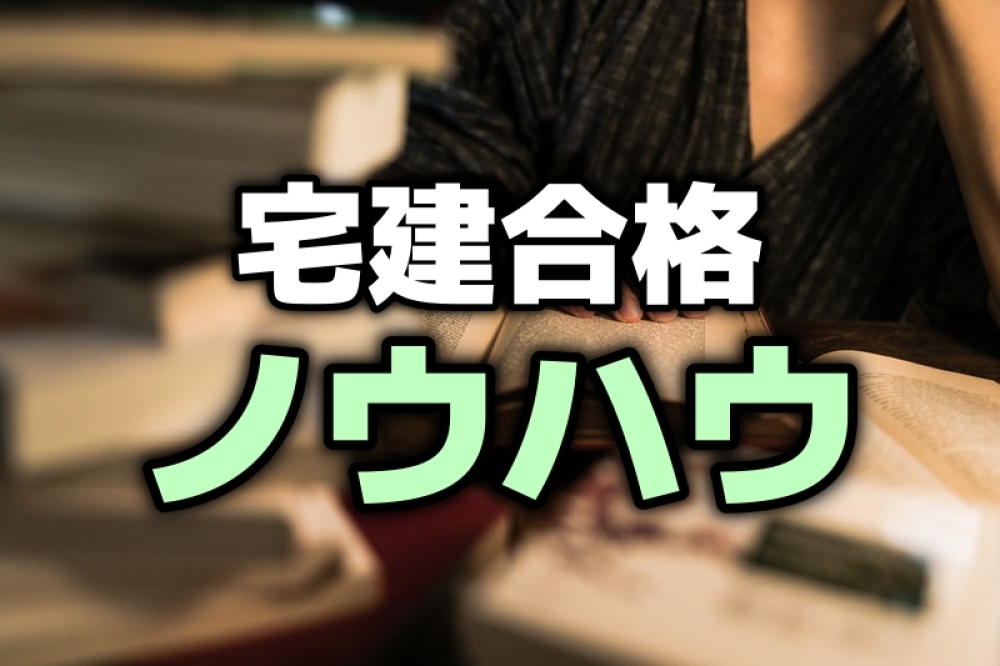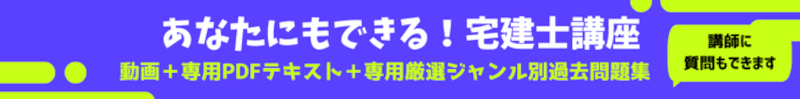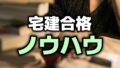今回のテーマは、勉強をいつから始めればいいか、です。
早すぎてダメ、遅すぎてももちろんダメです。
早く始めれば、勉強時間は確保できますが、モチベーションを維持するのが難しくなります。
遅ければ、もちろん、十分な知識を得ることができなくなります。
自分にとって、どのくらいの時間が必要かを見極め、適切な時期から勉強を始めることが大事です。
必要な学習時間は約300~500時間
この時間は、もちろん人によって異なりますが、このくらいの時間は必要だと言われています。
この時間を5か月間で消化するには、1日当たり2時間~3.5時間必要になります。
5か月で消化するのが難しいのであれば、8か月にすると、1日当たり1.25~2時間ということになります。
これを見れば、いつから始めればいいかが見えてくると思います。
あとは、自分にどのくらいの勉強時間があればいいかということです。
経験者は300時間?
経験者とは、例えば他の法律系の資格を持っている方や公務員の方、不動産業界などですでに働かれている方です。
こういった方は、すでに宅建試験で試験範囲の知識が多少あると思いますので、300時間程度で十分な方もいらっしゃると思います。
初学者は500時間を目安に
初学者の方は、500時間を目安に計画を立てるといいと思います。
次に、いつから勉強を始めればいいかという部分です。人によって違うと思いますので、タイプ別に解説していきます。
スタートは2月か5月
ここでは、初学者の場合で500時間を消化する場合を例にとってみます。
2月からスタートの場合では、試験まで約8カ月なので、1日当たり、1日当たり1.25~2時間取れれば、500時間に達します。
2月からであれば、比較的余裕があるので、忙しい人でも500時間を確保できるでしょう。
仕事があるときは1時間、休日は3時間くらい学習するイメージです。
5月の場合は、仕事があるときは2時間、休日5時間というイメージになると思います。
5月スタートの場合、かなりきついスケジュールになるかもしれません。平日の2時間もそうですが、休日5時間というのは、かなりのものかもしれません。
できれば、余裕を持った2月スタートをおススメします。
なかには、2カ月あれば合格できるという方もいますが、現実的かどうか…わかりますよね。
自分の場合は、2月からテキストを読み始め、5月のゴールデンウィーク明けから、本格的に勉強をしました。
別な記事で詳しく書こうかと思いますが、分野によって学習方法は変わります。民法とそれ以外では全く異なると言っていいかもしれません。
簡単に言うと、民法は時間が必要です。
どうしても時間がかかります。
宅建試験合格には、知識と経験が必要ですが、民法は知識ももちろんですが、経験がものをいいます。この経験は、ある程度時間をかけないと身に付きません。
5月スタートでも、イケる人もいますが、理想は2月ではないかと思います。
それより前はどうなの?
これも難しいかもしれません。この理由についても、後ほど紹介していきたいと思います。