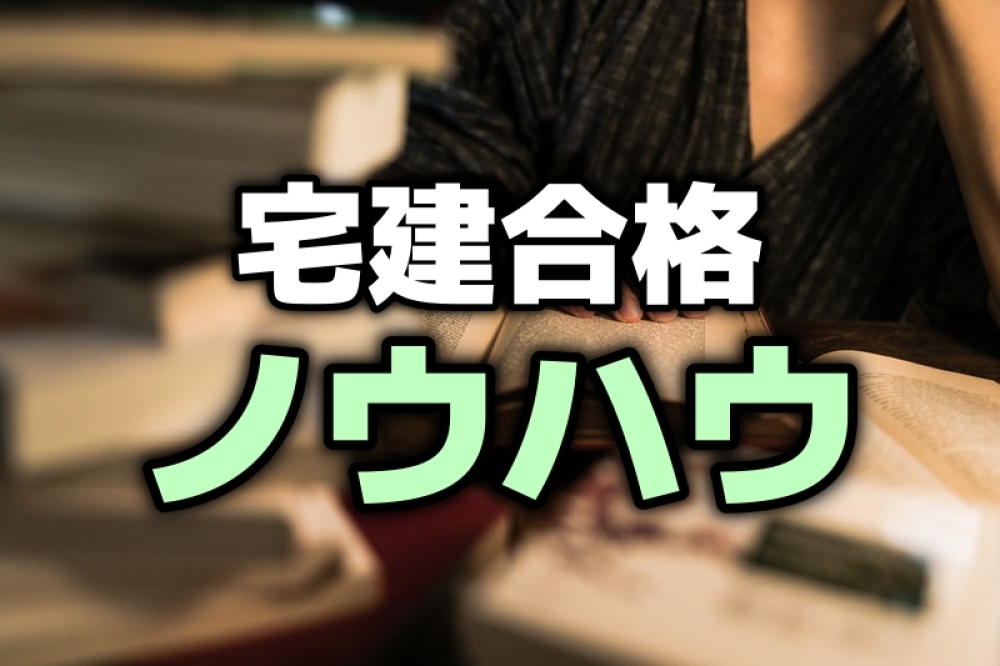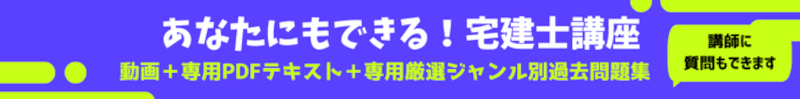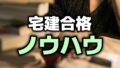こんにちは!
今回の記事は、2月スタートでの学習スケジュールです!
初めて宅建試験(宅地建物取引士)に臨む方は、どう学習していいか迷うかと思います。
特に宅建では、一般的に思い浮かべるような学習方法だけでは、合格できないこともあります。
これは、合格率の低さを見ればなんとなくわかると思います。
テキストを読んで、過去問をやる、コレだけでは、受かりにくいのが現状です。
そこで、今回は、2月スタートの場合のスケジュールを紹介していきます。
2月スタートでない方は、こちらもご覧ください。
2月から始めるなら、あなたにもできる宅建士講座
動画とPDFで独学合格を目指せる宅建士講座ができました!
ポイントを絞ったわかりやすい動画と持ち運び出来ていつでも見られるPDFのテキストで独学合格をサポートします。
2月スタートは、忙しい方にうってつけ
休日にしか、なかなか勉強できない方は2月スタートがおススメです。もしくは、ゆったりと学習を始めたい人も2月がいいのではないでしょうか。
2月~3月は権利関係中心
権利関係とは、民法、不動産登記法、借地借家法、区分所有法等です。特に民法は手ごわいので、雰囲気をつかむ感じではじめはスタートしていきましょう。
民法は、そんなに簡単に理解できません。
宅建試験でも、民法は10問出題されますが、40点以上取って合格される方でも、半分の5問程度の正答率だといわれています。
はじめは、理解できるはずはありません。焦らず、少しずつやっていきましょう。
具体的な方法としては、まずはテキストを読みます。ジャンルを絞って、例えば、「今日は制限行為能力者」といった感じで読んでいきます。
学生時代のように、ノートにまとめたりしなくても、私はいいと思ってます。本当に覚えられない部分だけをメモする程度でいいと思います。
そのジャンルのテキストを読んだら、過去問をやってみます。
過去問は、分野別過去問を購入しましょう。
過去問には、2種類あり、分野別過去問と○○年分過去問の2種類があります。その他、番外編として一問一答形式のもあります。
○○年分過去問は、本試験の内容をそのまま掲載したもので、分野別過去問は、過去問の中からその分野(ジャンル)の問題を抜き出したものです。
ジャンルごとに学習していきますので、分野別過去問を購入しましょう。
民法の過去問なんて最初は解けるわけない
過去問はいきなり解けません。解けなくても不安になる必要はりません。そういうものです。
繰り返しやっていくうちに解けるようになりますし、理解もできるようになります。この理解が非常に大事です。
最初は、テキスト読み→過去問→できれば翌日も同じ部分の過去問をやっていきます。
これを繰り返していきます。
後は、そのジャンルの学習を間隔をあけてやっていきます。
例えば具体的になこんな感じです。過去問を理解し、間違えなくなったら、もっと間隔を延ばしてもいいでしょう。
2/1 契約、制限行為能力者・テキスト読み
2/1 契約、制限行為能力者・過去問
2/2 契約、制限行為能力者・過去問
2/5 契約、制限行為能力者・過去問
2/9 契約、制限行為能力者・過去問
あとは、完全に解けるようになっても、半月~3週間に一度はその分野のテキスト、過去問をやっていきます。
先程の具体例の中に、開いている日があります。余裕があれば、この日に次のジャンルを入れていきます。
2/3 代理・テキスト読み
2/3 代理・過去問
2/4 代理・過去問
こんな感じです。
とにかく繰り返して、学習することです。
どんなに忙しくても30分は、宅建に触れる時間を作りましょう。これが、宅建に合格している人の特徴だと言われています。
少しでもいいので、宅建に触れない日を作らないことです。
上記の感じでやっていけば、3月の下旬ごろには、権利関係の終わりが見えてくるでしょう。
4月~7月は宅建業法と法制上の制限
2月から始めている権利関係をたまにやりつつ、4月からは宅建業法を始めていきます。
要領は権利関係と変わりません。
徐々に間隔をあけながら、テキスト読みと過去問を繰り返します。
これで、7月の終わりごろには、宅建業法と法令上の制限までが、1巡していることと思います。
ですが、まだこのころにはとても受かる気がしないと思うかもしれません。
また、この期間のどこかで、自宅でやるタイプの模試も購入しておきます。
8月からは税・その他、5問免除問題
法令上の制限が終わったら、残りの分野を学習していきましょう。
8月ごろになると、今年の税関連情報や法改正などが出そろってきます。
こちらも同じように、テキストを読み、過去問を繰り返してきます。
同時に、権利関係、宅建業法、法令上の制限も定期的に過去問を繰り返し解いてきましょう。
また、民法は分野別の過去問だけでは、足りない部分もあるので、感覚を身に着けるためにスマホのアプリで、過去問がありますので、ランダムで問題が出題されるタイプのものを選び、空いた時間でやってみてください。
9月は模試と直近の本試験問題
模試は、どのタイプを選んでも数回分掲載されていると思いますので、例えば4回分あれば、9月に3回、10月に1回やってみましょう。
模試も、1回だけやるのではなく、何回もやってみます。
直近の本試験も合わせてやってみましょう。模試と同じ感じで、1回だけは50問を一気にやってみます。同じように、これも繰り返しやってみましょう。
模試などをやっている間にも、過去問は繰り返し説いておきます。
分かっている問題でも解くことをおススメします。
以外に忘れているものもあり、半月に1回程度はやりましょう。
これで、合格に近づけるはずです。
合格できるかの決め手は、少しでもいいので宅建に触れない日がないようにということだけは忘れないようにしてください。
宅建試験頑張ってください!