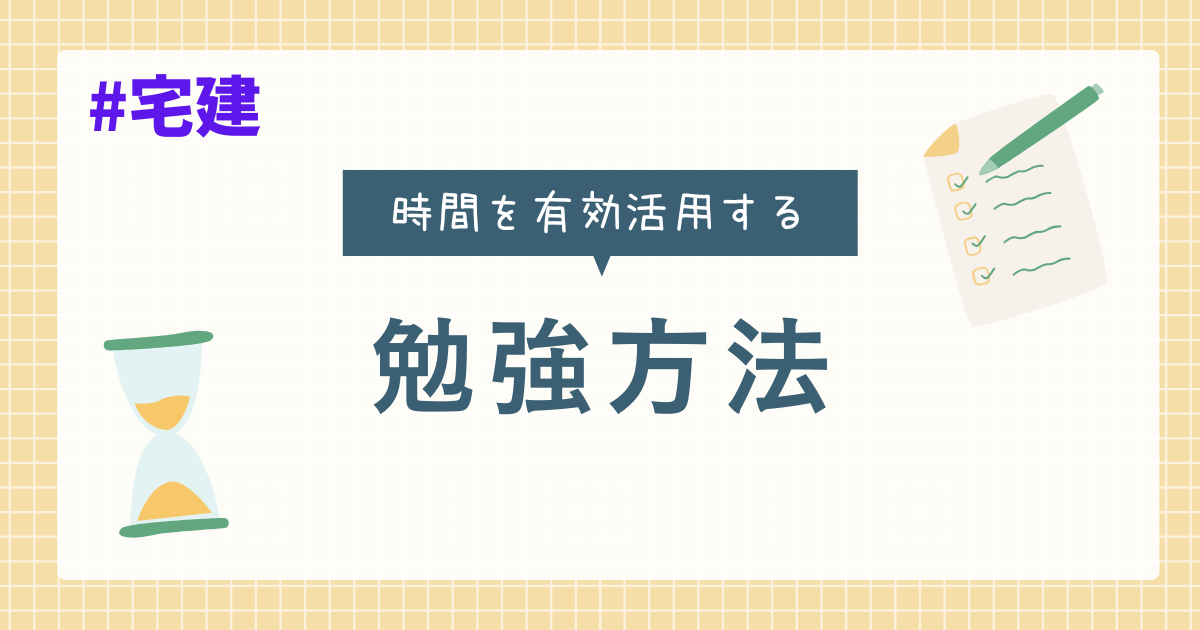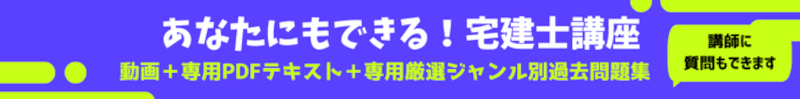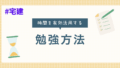こんにちは!
今回は「周辺知識を取り違えると大変なことになる」というテーマです。
よく、SNS等で、宅建の過去問題集を解いていて、「周辺知識を一緒に学習しよう」と紹介されていることが多くあると思います。
周辺知識ってなに?
周辺知識とは、その問題や選択肢では直接問われてはいないけれど、同じテーマの知識のことです。
例えば、国土利用計画法で、市街化調整区域の届出が必要な規模が過去問で問われたとします。その時に他の区域での規模を確認するというのが、周辺知識です。
この周辺知識の意味を取り違えると、不必要に学習範囲を広げたり、意味のないテキストに載っていないことを追いかけすぎで自爆するということもあります。
また、SNSでは、初見の問題がいっぱいでる!と不安をあおってくる場合もあります。
これは、誤りではありませんが、正確には、完全に初見の問題は数問です。初見の選択肢は、そこそこ出ます。
でも、宅建試験は、基本4択です。一部権利関係や宅建業法では、完全な4択ではない、個数問題が出ることもあります。
とはいえ、完全な初見問題は思ったよりかはでません。
宅建試験は、言い方を変えたり、数字が変わっていたり、状況が変わっているだけで、基本的には過去に問われた内容が出ているのがほとんどです。
もし初見の選択肢が出ても、基本4択ですから、しっかり勉強した人であれば、正解を2つまでは絞れると思います。
あとは、この2択からどちらが、そうらしいかを決めるだけでいいんです。
このように、初見の問題が出たときに、学習範囲を不必要に広げて対応するのではなく、問題を解ける力を見つけることも大切です。
初見の問題が出たらどうしようという不安から、周辺知識の意味を取り違え、SNSに煽られながら、どんどん学習範囲を広げて、基本的な知識を忘れ、出るか出ないかもわからない知識を周辺知識と勘違いして無駄に学習しているケースが多々あります。
そうならないように、しっかり見極めていきましょう。
周辺知識とは、その問題には出なかったけど、ついでに確認しておきたい基本的な事項だということを忘れないでください。