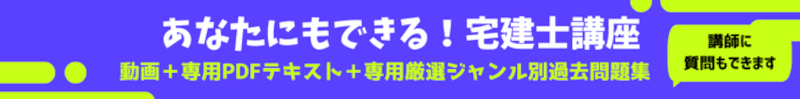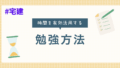宅建試験勉強を始めて、一番最初の壁が民法ではないかと思います。
こういったことから、試験勉強のスタートを宅建業法にした方がいいという意見もあります。
ただ、民法がベースで宅建業法がその上に乗っている部分もありますので、民法からスタートすることをおススメしています。
その詳しい理由はこちらで
今回は、権利関係のジャンルの中でも民法のお話です。
民法は最初、さらっとやればいい
民法は、宅建の試験範囲で一番難しいです。
民法は試験で10問出題されますが、合格している人でも5問程度正解という方も多いですようですし、5問程度正解できれば、他のジャンルで頑張れば、40点に達することも難しくはありません。
そういった、気持ちで勉強に取り組んだり、問題を解くことがまずはポイントといえます。
それだけ、民法は難しいですし、問題的にも民法の中の様々な条項から複合的に出題されることも多く、試験では、テキストに載っていない、初見の問題も「どうせ出ます」
それくらいの気持ちで臨むのがいいと思います。
試験勉強をしていくと、少しでも点数を取りたいという気持ちから、どんどん勉強する範囲を広げたくなりますが、やめた方がいいと思います。
やればやるほど、自信を無くしていくと思いますし、他の得点するべき問題を落とすきっかけにもなってしまいます。
民法は最初、さらっとやればいいんです。
特に、民法では、聞きなれない用語などが出てきます。
その意味はまず押さえておきます。例えば、善意無過失とか契約不適合責任とかです。
詳しい内容は、最初はテキストを読んだり、動画を見たりしてさらっと流しましょう。
何となく理解できればOKです。
民法で重要なのは、問題を解けるか、どうか
テキストの内容を理解するのと問題を解けるのかは実は、別な問題です。
民法の問題は、他のジャンルと一線を画します。
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
こちらは、令和元年本試験の問題です。
民法の問題では、登場人物が何人か登場したり、問題文に条件がいろいろと書かれることがあります。
つまり、問題文をよく読まないと回答できない問題が多く出ます。
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
こちらも、問題文ですが、実は問題文を読まなくても回答できます。
宅建では、選択肢の中からどれが間違っているか、あっているかを選択する問題が多く出ますが、問題文を読まなくても、選択肢を「〇」か「×」か考えていくと、誤りを探すのか、正しいものを探すのかもわかります。
民法は、単純な知識を問う問題だけなく、状況を整理して解く、複雑な問題も多く出ます。つまり、テキストを読んだだけでは回答できない問題も出るということです。
これを攻略するには、問題の形式に慣れることが大事です。
他のジャンルと決定的に違うのは、とにかく問題に慣れるということです。
テキストはさらっと読み流し、まずは過去問をやってみてください。
それも、1問1答形式ではなく、本試験と同じ4択問題をやってみてください。
はじめは、誤答ばかりでなえるかもしれませんが、そのうち慣れます。
慣れると、初見の問題でもなんとなく分かるようになってきます。
もちろん、全部それで正解できるわけではありませんが、初見の問題が怖くなくなります。
民法は奥が深いので、ここには一度に書き切れませんが、まずはこれらを意識していくと合格につながっていくと思います。
合格された方の多くは、このコツをつかんだのではないでしょうか。