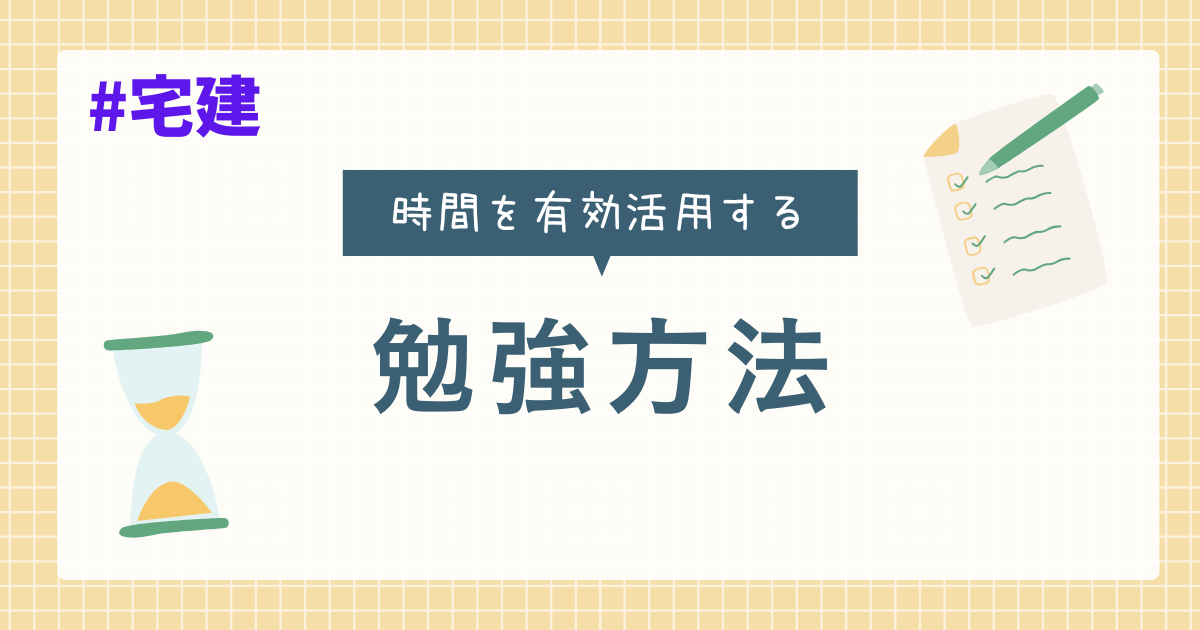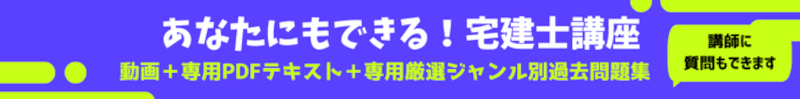こんにちは!
今日のテーマは、宅建を一発合格した人がやったすべてのことです。
私が合格した時に行った勉強法、やらなくてもよかったこと、やってもよかったことなどのノウハウをすべてお伝えしていきます。
7月まで
ご存じの通り、7月1日から宅建試験の申し込みが例年スタートします。この申込みをするまでにある程度勉強しておくことが大事です。
この申込みまでに、ほとんどしていないと、なかなかモチベーションがあがりません。申し込んでからしっかり勉強しようと思っても難しい場合もあるでしょう。
ただし、だからと言って7月から勉強を本格的に開始してもまだ大丈夫です。十分取り戻せます。
まず5月中旬くらいから勉強を始めました。最初はテキストを読んで、その分野の過去問を解くというのを繰り返しました。詳しくはこちらに書かせてもらいました。
過去問は、間違えたところは翌日も解き、正解したところは少しずつ間隔をあけて、繰り返すようにしました。試験までは、間違えないとわかっていても、15日に1回くらいはその問題を解いた方がいいでしょう。
週に単元を3~5個ずつ進めていきます。これで、8月までには、一通り終わっていることと思います。
もし、これから本格的にやられる方であれば、やはり8月末までには一通り終わっていることを目標にして、スケジューリングするといいと思います。
過去問の選び方
過去問は、分野別過去問が1冊あれば十分です。肢別(4択が分かれているもの)は必要ありません。なくても合格できます。もちろん、そのあたりは好みなので、購入することを止めませんが、分野別過去問題集(4択)があれば十分でした。こちらにも詳しく書かせていただきました。
ちなみに、なぜ肢別ではないかというと、結局受験して分かったのですが、試験は4肢だからです。
最近では、宅建業法を中心に個数問題が多く出題されるようになり、4択だからと言って、消去法で答えが導き出せる問題が減ってきています。とはいえ、宅建業法はそれでも対応できますし、民法に関しては、肢別をやったからと言って、それでも難しいです。
肢別は、知識を確認するもの
4択の問題集は、問題を解く力を身に着けるもの
こういった違いがあります。結局は、試験と同じ形式の問題を数多く解いた方がいいということが実際に受験してみてわかりました。
実はテキストってそんなに繰り返し読みません
テキストをしっかり読んだのは1回だけです。あとは、辞書代わりに使っていました。
テキストは、意外に余分がモノが多いからです。
ですから、自分はそこから要点を抜き出した資料を作成しました。これを試験まで繰り返し確認していました。試験会場にも持っていき、当日の確認にも使っていました。
それをもとにした、ものがありますので、よかったらこちらからどうぞ
この資料が意外に役に立ちました。テキストはこれ以降ほとんど触らなくなりました。
9月になったら、模試
9月の中旬ごろから模試を始めました。模試は、本で売っているタイプのものです。
9月中旬ごろから週1回それに取り組みました。
4回分がついているものでしたが、だいたい42~44点くらいでした。本試験が44点(自己採点)でしたので、模試の結果と本試験の結果にはあまり差異がないことがわかります。
模試の結果は、比較的信用していいのではないでしょうか。
知識も大事だけど問題を解く力の方が大事
本試験には、どうせ見たこともない問題が出ます。
コレの対策は、知識を広げることではありません。
宅建は満点を目指すと落ちるとよく言われますが、まさにこれがそうです。
どうぜ、見たこともない問題が出るわけですから、知識を広げるよりも問題を解くコツをつかんだ方が役に立ちます。
これも肢別をあまりおススメしない理由です。肢別ではこの力は身に付きません。ですから、模試はけっこう重要です。
模試も過去問と同じように繰り返してもいいと思います。
特別なことはしなくても合格できます
自分が買ったものはテキスト、分野別過去問題集、模試だけです。
とにかく重要なのは、続けることです。
もうこれくらいでいいだろう、今日はいいだろうでは合格するのは難しいかもしれません。
宅建試験は、合格率1割台の落ちる人の方が圧倒的に多い試験です。
勉強が習慣化されている人は合格しやすいと言われています。
どんなに疲れている日でも、10分は最低何かをしましょう。
明日何をするか、今日何をするかは、勉強する前に決めておきます。決めないと、今日はいいやになってしまいます。
自分は、勉強を始めてから一切勉強をしなかった日が一日もありません。これが、最大の秘訣かもしれないです。