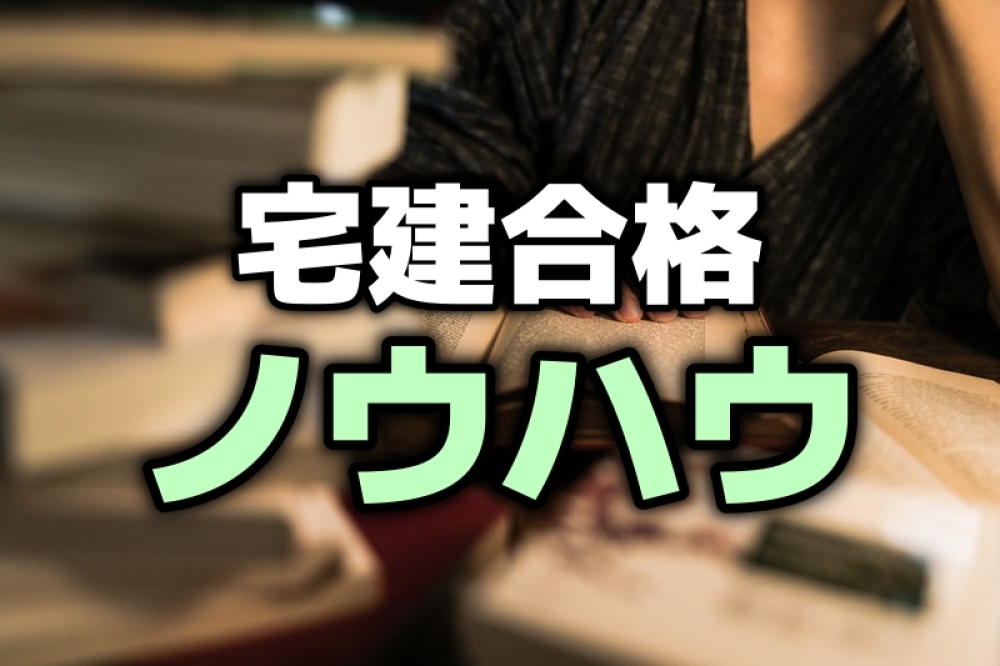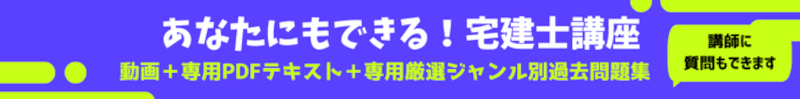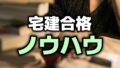こんにちは!
今回は「宅建の問題には3種類しかありません」です!
宅建(宅地建物取引士)試験は、全50問ありますが、大きく分けて3種類に分かれるということです。この3種類を理解できれば、効率のいい学習方法が見えてきます。
逆に言うとこれがわからないままただ漫然と学習していると、不要な知識まで入れようとしてドツボにはまっていき、今までわかっていた問題が解けなくなります。
また、試験が近づくにつれてどんどん不安になり、結局受からない、ということにもなりかねません。
合格した人の話を聞くと、捨てる、確実に拾うを行っている人が多く、この3種類を意識して勉強していたことが見えてきます。
もう二度と出ない問題
3種類のうち一つは、「もう二度と出ない問題」です。
二度と出ないというと少し大げさですが、過去問でもめったにお目にかからない、ずっと出ていないテーマの問題です。
これは、もう捨ててもかまいません。
内容的に、覚えるのが難しくなく、他と連動して覚えやすいものでしたら、覚えておくのも手ですが、何度も繰り返し学習して身につけるほどのものではありません。
宅建は50点満点を目指す試験ではありません。38点取れればかなりの確率で合格、40点でほぼ間違いなく合格ですから、そのあたりを目指せばいいわけです。
ですから、10問は間違ってもいいわけです。
どうしても覚えられない、苦手なテーマがあれば、多少は捨ててもいいんです。
例えば、民法では詐害行為取消権があります。
過去に出題されたことがあるので、載っているテキストもありますが、出ない確率が高いのに、けっこう複雑です。
初学者の方は、捨てていいテーマだと思います。もちろん、今年の試験に出ないとは限りませんが、こういうものをすべて追っていると、本来落としたくない問題を落とすきっかけになってしまいます。
「そういうものがあるんだ」くらいにとどめておきましょう。
たまに出る問題
文字通り、2年続けて出ることもありますが、2年続けて出ないこともある問題です。
例えば、相隣関係なんかはそうです。
出ないことはないけど、あまりでません。
この手のテーマは、とりあえずテキストは読んでおくけど、最初のうちは流してもかまいません。
勉強し始めは、テキストを隅から隅まですべて理解しようと躍起になるかもしれませんが、基礎を固めるのが大切です。
例えば、抵当権はしっかりやるけれど、根抵当権はそういうものがあるくらいに学習しておきましょう。ただ、根抵当権はたま~に出ますので、余裕があれば簡単に学習しておきます。
こういった感じで、捨てるテーマが多少あっても、40点は十分とれる可能性があるからです。
こちらで得点計画に触れていますが、民法は10問中5問正解で十分40点超えられます。
半分正解でいいんですよ。
この気持ちが合格につながります。
繰り返し出る問題
最後に「繰り返し出る問題」です。
これには、似た問題も含まれますが、テーマとしてよく出る問題です。
例えば、民法だと相続、抵当権、制限行為能力者は近年よく出てきます。それ以外にもありますが、これらはしっかり学習しておきます。
この繰り返し出る基礎的なテーマをしっかりやっておけば、十分に合格点にたどり着けます。
ちなみに、宅建業法は全部これに入ると思っていいでしょう。
細かく見れば、もう二度と出ないテーマもありますが、宅建業法は、18~20点取るのが難しくないジャンルでもあるので、ここに入ります。
これら3種類を意識して過去問に取り組むといいでしょう。
特に、年度別過去問(基本的に、本試験の内容が順番そのままに掲載されている問題集)では、この切り分けが大切になりますので、学習の参考にしてください。