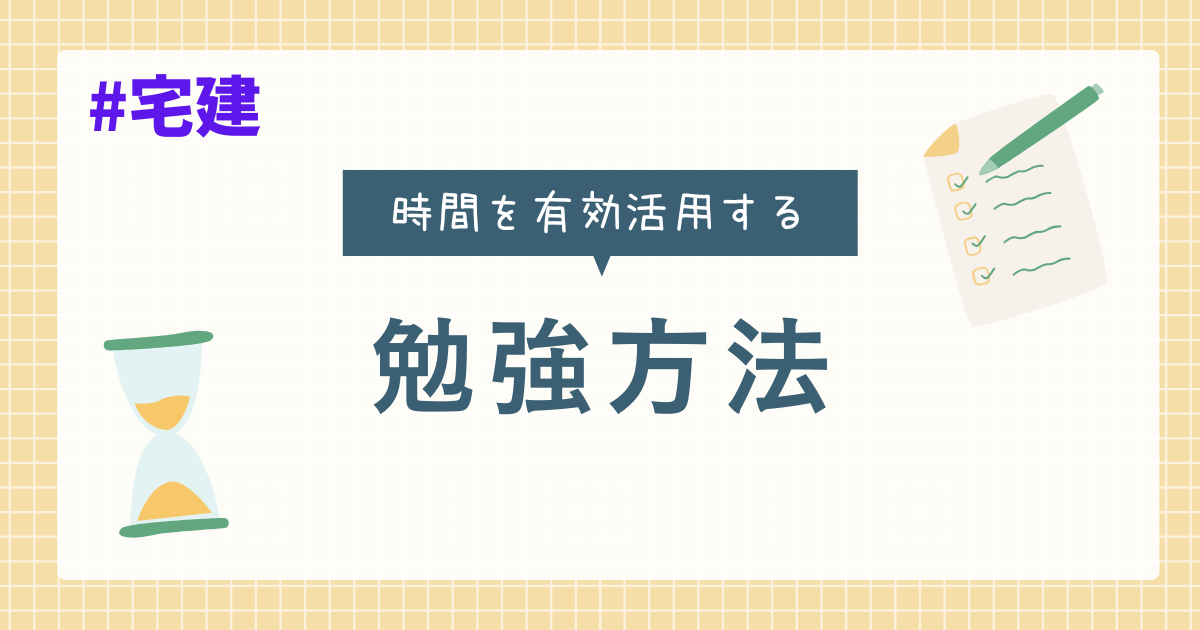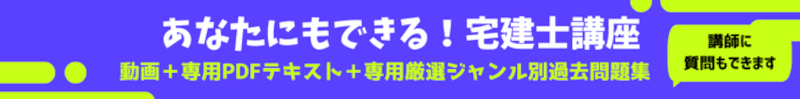こんにちは!
今日のテーマは、宅建(宅地建物取引士)試験の内容が3年位前から難しくなっているというお話です。
結論から申し上げますと、すべてのジャンルではないのですが、確実に難しくなっています。
令和6年・問21(農地法)
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を原因とする所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも、農業委員会の許可が必要である。
- 法第5条第1項の許可申請書の提出において、法ではその申請に係る権利の設定又は移転に関し民事調停法により調停が成立した場合など一定の場合を除き、当事者は連署した申請書を提出しなければならないとされている。
- 法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされる。
- 法では、農地の賃貸借の当事者は、当該賃貸借の合意による解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合など一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、当該賃貸借について、解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知をしてはならないとされている。
これが、令和6年に出題された農地法の問題です。
農地法というと、3条(権利移転)、4条(転用)、5条(権利移転+転用)において、許可が必要か、届出でいいのかなどがよく問われてきましたり、ほとんどのテキストもこれがメインに書かれています。
しかしこの選択肢を見ていただくとわかる通り、テキストに基本事項として載っているものは一つもあります。
選択肢4は、テキストによっては載っていることもありますが、「こそっと」、もしかしたら出るかもしれないよ、程度に記載されている程度がほとんどではないでしょうか。ちなみに、令和3年の問題にも出ました。
ただ、選択肢4が分かったとしても、選択肢4は、あっていますから、この問いの正解を導くまでには至りません。
農地の賃貸借
農地法では、農地の賃貸借を解除などする場合に、知事の許可を受けなければならないとされています。
農地法18条
農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。
このように規定されています。
もちろん例外もあります。ちなみに調停や、期限の6カ月以上前に文書によって合意されている場合などでは許可不要です。
選択肢2
法第5条第1項の許可申請書の提出において、法ではその申請に係る権利の設定又は移転に関し民事調停法により調停が成立した場合など一定の場合を除き、当事者は連署した申請書を提出しなければならないとされている。
これももしかしたらわかるかもしれません。どのテキストに書かれている知識ではありませんが、5条許可は、売る側と買う側の二人が関わっていますので、連署が必要だろう、と想像することはできるかもしれません。
ただし、「民事調停法の調停」といいった、見慣れない文言が本試験中に飛び出してくると、この問題難しいと思ってしまうかもしれません。
農地法の変化
正解は1で、仮登記には農業委員会への許可はいりません。消去法で何とか、答えられた方はいるかもしれませんが、今まで得点源であった農地法でいうと、難問だったでしょう。
得点源が減っている
他にもこういったジャンルはあります。国土利用計画法がその傾向があります。
今までの勉強方法では、対応できなくなっているのは間違いないでしょう。
従来の過去問+テキスト方式では限界が…
これまでは、テキストを確認し、過去問を繰り返し解くだけで、合格できていたかもしれません。
これからは、それはもちろん必要です。過去で問われた知識が、繰り返し問われるという基本は変わっていません。
ただし、それにプラスアルファが必要ということです。
市販テキストに限界を感じたら…?
市販のテキストは、いろいろな人が手に取りますので、汎用的になっています。この事実に気づいた方の多くは合格していますし、ただ漫然と学習していた人の多くは、不合格であったというのは仕方のない話です。合格率が2割を割る国家資格ですから、その通りです。
本屋さんだけでは限界の時代到来
本屋さんに並んでいる書籍は、たいていその年の試験が終わった直後に発売されます。
ですから、直近の傾向に対応していないテキストも多くあります。
宅建は、ご存じの通り簡単な試験ではありませんから、かなり前から学習をスタートしたいと思っている方も多くあります。
できるだけ、早くテキストを売り出した方が売り出した方がいいわけですし、本の出版には時間がかかりますので、どうしてもそういった傾向が出てしまいます。
あなたにもできる!宅建士
あなたにもできる!宅建士講座では、その直近の傾向に対応したテキスト+過去問を提供しています。
また、テキストや過去問題集だけではなく、動画(広告は入りません)、模試や、本試験直前期には追加要点、本試験会場に持って行って、試験前に要点の確認ができる追加テキストも提供予定です!
さらに、講師に質問ができるのも魅力です。
宅建の合格率は17~15%が標準ですが、その中で、一発合格する人は半分しかいないと言われています。
全受験生の中で、1回で合格する人は、10%に満たないと言われています。
それでも、年1回の試験ですから、一発合格したいのは本音ではないでしょうか。
なりふり構わず、学習している人が合格しているともいえる、宅建士試験の中で、いろいろな方法を試してみましょう!