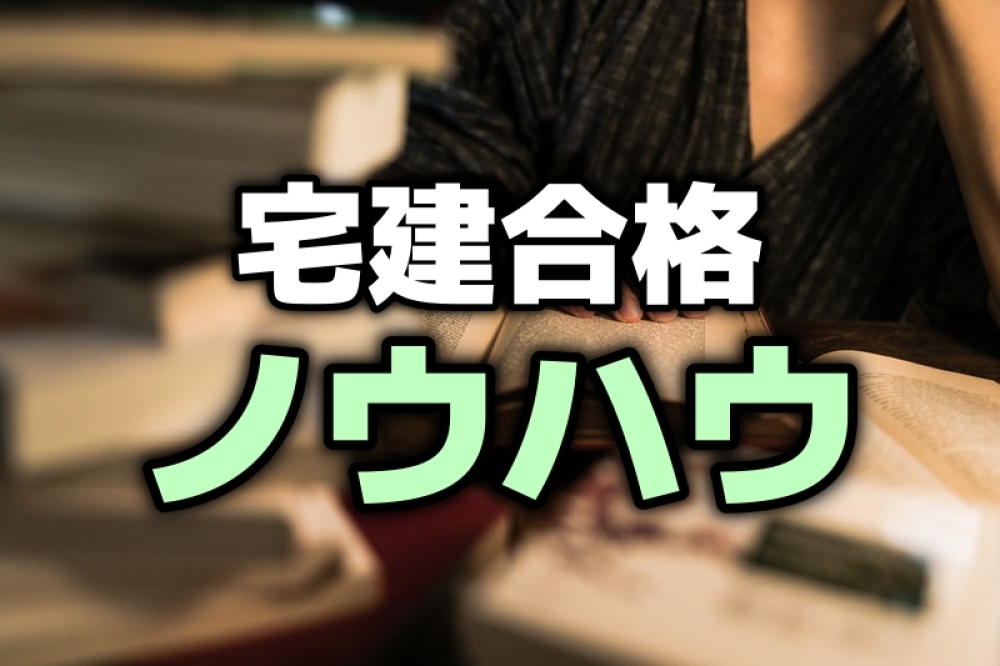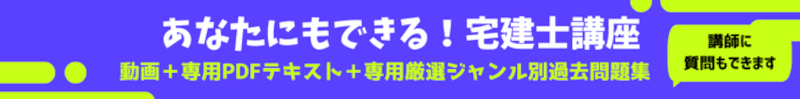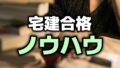宅建(宅地建物取引士)の試験勉強を漠然としていませんか?
テキストを書かれている順に読み、過去問を解く、を繰り返す。
このように漠然と勉強していると落ちます。
宅建試験の合格率が低い一つの理由に、勉強方法が間違っていることが多々あります。
勉強時間が足りていても、落ちてしまう…そうならないためにはどうすればいいでしょうか…
漠然と勉強してはいけない理由
まず、宅建の試験範囲は非常に広いものとそうではないものがあります。
宅建には以下のジャンルがあります。
- 権利関係
- 宅建業法
- 法令上の制限等
- その他(税、5問免除問題など)
大きく分けるとこの4つです。
この中で、試験範囲が広いのは、宅建業法以外の分野です。
宅建業法はも狭いとまではいいませんが、全50問中20問が、宅建業法であることを考えると、それなりに時間をつぎ込んで勉強する必要があります。
権利関係は勉強の仕方を間違うとアウト
ざっくり権利関係といってもかなり幅が広いです。
明確に比較はできませんが、どのテキストでも、だいたい権利関係は最も分厚くなっています。宅建業法の1.5倍くらいあるテキストがほとんどではないでしょうか。
にもかかわらず、権利関係の出題数は14問です。
14問と宅建業法20問に比べて少ないのに、テキストの量は1.5倍です。
さらに言うと権利関係では、テキストに載っていない問題も必ず出ます。
権利関係は、さらに細分化できます。
- 民法(10問)
- 借地借家法(2問)
- 不動産登記法(1問)
- 区分所有法(1問)
権利関係は、民法とそれ以外に分けられます。
それ以外(借地借家法、不動産登記法、区分所有法)は比較的得点しやすい分野です。しっかり勉強すれば、4問中3問は正解できるはずです。
さらに民法でも毎年高確率で出題されていて、得点しやすい分野がいくつかあります。
- 相続
- 抵当権
- 時効(取得時効)
これらは、出題率の高いテーマです。出題率が高いので、しっかり学習した方がいい分野です。
権利関係の得点計画
権利関係の目標点は7/14問くらいといわれています。半分正解すれば、合格に近づけるといわれています。
半分正解できれば、十分に合格ラインに達するといわれています。
おそらく昨年(2024年)の合格点37点ですから、権利関係で7点取れていれば、全部で37に達するのは可能ではないかと思います。
この7点のうち、先ほどのそれ以外(借地借家法、不動産登記法、区分所有法)で3点、出題率の高いテーマ3つのうち、2点取れれば、すでにこれで5点です。
あとは、残りの6~7問で、2点くらい取れれば、7点になります。
いくら、テキストに載っていない、チンプンカンプンな問題が登場しても、6~7問の中には、それだけではない、どのテキストにも載っているような、制限行為能力者、意思表示、代理、物権変動の対抗問題、不法行為、弁済、相殺といったジャンルも何問かは登場するでしょう。
このような感じで、メリハリをつけて勉強することが大事です。
学習を進めていくと、知らない問題が出たらどうしようと不安になると思います。
私もなりました。
特に、YouTubeやSNSでは、それにフォーカスしているものもあり、どんどん漫然に勉強するようになってしまいます。
どこが、重要なのか、どこを捨ててもいいのかしっかりと仕分けるのがまずは大事です。
そのためには、得点計画は重要です。